はじめに
自分は管材業界で10年以上、代理店営業として日々現場への搬入・納品に携わってきました。
塩ビ管や鋼管、継手などの資材は、ただ倉庫から届けるだけではなく、安全かつ確実に現場へ届けることが最も重要です。特に、トラックでの運搬・積載・現場対応は、営業・配送スタッフにとって絶対に欠かせない知識と技術になります。
今回は、これまでの経験をもとに、管材運搬におけるトラック運転の注意点10項目を徹底的に解説していきます。
① 長尺パイプの積載は「突出」に注意
塩ビ管やライニング鋼管、鉄管などは、4m~5.5mと非常に長いため、トラックの荷台からはみ出す場合が多いです。
- 基本ルール:車両の全長の10%までの突出はOK
- それ以上は警察への申請(制限外積載許可)が必要
- はみ出す場合は赤い布を取り付ける義務があります
🔧 対策
- はみ出さない積載方法を検討(斜め積み・荷台中央配置)
- 長尺対応のトラック(ユニック・ロング平)を使用
② 荷崩れ・バランスに注意!重い管は下、軽い管は上
重量物(SGP、ライニング管など)を積む場合、積み方ひとつで走行中の安定性が大きく変わります。
- 重い管を下・軽い管を上
- 左右均等に積載して偏荷重を避ける
鋼管は何本かまとまるとかなりの重量になるため、現場によってはリフトですくったり、クレーンで持ち上げることも多いです 下に板木などを強いいておくことを推奨します
③ 必ず輪止め&ロープ固定!油断は事故につながる
✔ 輪止め
- 荷降ろし中にトラックが動き出すリスクを防止
- 特に坂道や傾斜のある現場では必須
- 現場によっては必ず必要と言われることがある
✔ ロープ・ラッシング
- 2点以上の固定+斜めにもベルトをかける
- 長尺パイプは走行中にわずかにズレるだけでも後方へ大きく飛び出す
④ トラック初心者が気をつけたい5つの運転ポイント
通常の乗用車と大きさが違うので最初運転するときは戸惑うと思います 以下に注意点をまとめてみました
| 項目 | 注意点 |
|---|---|
| 小回り | 通常車より大きく回る意識 |
| 後方視界 | ミラーと目視を併用して慎重に |
| 高さ制限 | 車高+積載物の確認を忘れずに |
| 積載反応 | 急ブレーキ厳禁、ふわっと運転 |
| 停車位置 | 出入り口・歩道・植栽にも注意 |
トラックは「大きいだけ」でなく、事故を起こしたときの責任も大きいので、常にゆとりある行動が求められます。
⑤ 現場は毎回違う!ナビ+事前確認が超重要
管材の現場搬入先は、毎回違う現場です。しかも…
- Googleマップでは道があっても実際には狭い
- 進入ルートが複雑なケース(工場裏口など)も多数
- 電柱や植木などの障害物が多い
🔧 対策
- トラック対応ナビアプリ(Yahoo!ナビ、ナビタイム)を活用
- ストリートビューで進入口を事前確認
- 先方に「2t車で入れますか?」などの確認も◎
⑥ 事故・トラブルの備えにドライブレコーダーを!
現場周辺は住宅地・工場地帯・歩行者の多い通路などが多く、接触事故のリスクが高めです。
- 積み荷が飛び出して他車に当たる
- バック時に壁・車に接触
- 「時間通りに来てない!」などの言った言わないトラブル
📷 ドライブレコーダーを設置しておけば、証拠として残せます。
おすすめ機能:
- 前後2カメラ+車内カメラつき
- 駐車監視モード
- Wi-Fi転送対応モデル
⑦ 【年代別】自分の免許で運転できるトラックは?
意外と知られていませんが、同じ「普通免許」でも取得年によって乗れるトラックが違います。
| 取得年 | 免許区分 | 運転できるトラック |
|---|---|---|
| ~2007年6月1日 | 普通免許(旧) | 5t未満の車両(2t~3tOK) |
| 2007年6月~2017年3月 | 中型8t限定 | 積載3t・総重量8t未満 |
| 2017年3月以降 | 準中型免許 | 2t車までが制限付き(注意!) |
🚛 免許と車両重量が合っていないと、違反になります。
| トラックの仕様 | 必要な免許区分 | 備考 |
|---|
| 最大積載量 2t未満 / 車両総重量 3.5t未満 | 普通免許(現行) | いわゆる「小型トラック」 |
| 最大積載量 2〜3t / 車両総重量 3.5〜7.5t未満 | 準中型免許 | 2017年以降の普通免許ではNG |
| 最大積載量 3t〜4.5t / 車両総重量 7.5t〜11t未満 | 中型免許(限定なし) | 一般的な「4tトラック」に相当 |
| 最大積載量 6.5t以上 / 車両総重量 11t以上 | 大型免許 | 大型トラックの範囲 |
⑧ 積み下ろし時のケガ・破損防止にも注意!
- 下ろすときにパイプが転がる、弾む、滑る
- 特に雨天や凍結時は荷台が滑りやすく危険
- トラックと地面の段差で膝などが痛い方にはあおり用ハシゴを利用も推奨します
🧤 滑り止めマットの活用、作業手袋などの装備も重要です。
⑨ 給油の確認とアドブルーの補充
🔹 給油ミス注意!トラックは軽油が主流
多くの2t~4tクラスのトラックはディーゼルエンジン搭載のため、
燃料は**ガソリンではなく「軽油」**です。
【注意点】
- セルフ給油所で間違ってレギュラーガソリンを入れてしまう事故が時々発生
- ガソリンを入れてしまうとエンジンが故障し、修理費が数十万円かかることも…
🔧 対策
- 初めて乗るトラックでは給油口に「軽油」と書かれているか確認
- 紛らわしい場合は、事前に車検証や車両仕様書で確認しておく
🔹 アドブルーとは?排ガス浄化に必要な尿素水
近年のトラック(特に平成22年以降の排ガス規制適合車)では、
「アドブルー(AdBlue)」と呼ばれる尿素水の補充が必要になります。
アドブルーは、排ガス中の有害物質(NOx)を分解して、クリーンにするための添加液です。
【ポイント】
- 専用のタンクに軽油とは別に補充する
- 使い切るとエンジン始動制限がかかる車種もある
🔹 アドブルー警告灯が点滅したらどうする?
警告灯のパターンは車種によって異なりますが、一般的には以下の流れです。
| 警告段階 | 意味 | 対処 |
|---|---|---|
| 点灯(黄色) | 残量少ない | 補充準備する(2000km程度走行可) |
| 点滅(黄色) | 残量かなり少ない | 早急に補充。100~300kmで始動制限あり |
| 点滅(赤)or始動不可 | アドブルー空 or 異常 | 補充+場合により故障診断が必要 |
🔧 補充方法
- 軽油と同じように給油所でアドブルー(専用ノズル or 容器)を補充
- 必ず専用品を使う(誤って水などを入れない)
🛠 補充を怠るとどうなる?
- エンジンがかからなくなる(始動ロック)
- 排ガスエラー表示 → 整備工場行き
- 排ガス規制違反になる可能性あり
アドブルーは消耗品であり、燃料のように定期補充が必要です。
4tトラックで約1000〜1500kmごとに10L前後消費するイメージです。
✅ 実務的なワンポイント
- 納品の前日に軽油とアドブルーの両方をチェックする習慣をつける
- アドブルーは下記で購入可能
⑩ 荷物が飛ばないように、また雨天時の濡れ対策にシートは必需品
🔹 1. 荷物の飛散・落下を防ぐ役割
特に軽量な塩ビ管やダンボールの箱 ポリエチレン等の配管材は、風の抵抗で飛ばされることがあります。
高速道路やバイパスでは、少しの風圧でも荷物が動くことがあり、重大事故にもつながりかねません。
🔧 シートで全体を覆い、風を直接当てないようにすることで飛散リスクを大幅に軽減できます。
🔹 2. 雨による濡れ・劣化の防止
管材には水濡れに弱いものもあります。
| 材料 | 雨の影響 |
|---|---|
| ダンボール梱包の継手類 | 濡れると崩れる・変形する |
| スチール製継手・部材 | サビや腐食が発生する可能性 |
| テープ巻き済みのパイプ | 粘着力が落ちたり、剥がれる恐れ |
🔧 シートをかけることで、急な雨・夜露・霜などの水分から資材を守ることができます。
まとめ:トラック運転も「段取り力」が命
管材業界におけるトラック運搬・現場搬入は、
単なる運転ではなく、“安全・確実・信頼”を届ける仕事です。
✅ 長尺物の積載
✅ 荷崩れ防止
✅ 免許の確認
✅ ナビ&ドラレコの活用
✅ 初心者向け運転マナー
どれも「事故を防ぎ、現場に迷惑をかけない」ために必要な視点です。


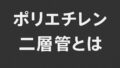
コメント